ある日ふと気づくと、あなたは子どもの手を引きながら、保育園を探している。どこも笑顔の写真、整ったカリキュラム、そして「高評価」。だけど、ふと立ち止まって思う。「この“評価”って、いったい何を評価してるんだろう?」と。
その疑問の答えを、少しだけ掘り下げてみた話です。
📌この記事でわかること
- 「福祉サービス第三者評価」って、そもそも何?
- どうして評価されているのに、保育の違いがわからないの?
- 評価と、子どもの発達って本当に関係あるの?
- 本当に“意味のある評価”にするためには、何が必要なのか?
論文の執筆者について
- 藤澤 啓子(ふじさわ けいこ)
慶應義塾大学と東京財団政策研究所に所属。教育政策・保育政策を研究する専門家。 - 杉田 壮一朗(すぎた そういちろう)
同じく慶應義塾大学と東京財団の研究者。教育とデータ分析に詳しい。 - 深井 太洋(ふかい たいよう)
筑波大学の研究者で、保育・教育現場の実証研究に携わる。 - 中室 牧子(なかむろ まきこ)
教育経済学の第一人者。TVや書籍でも活躍する慶應義塾大学の教授。
第三者評価を積極的に受けている保育園がたくさんある。評価機関がチェックし、保護者のアンケートも取り、結果はネットで公開されている。数字は並ぶ。「達成度:5点中5点」「保護者満足度:98%」。
でも、その高評価の行列をじっと見ていると、ちょっと不思議な気分になる。
どの園も高得点、どの質問もポジティブな答えばかり。まるでどの園に入れても同じように見えてくる。だとしたら、保育の“質の違い”って、いったいどこにあるんだろう?
論文を書いた研究者たちは、こう問い直した。
「この評価って、本当に“質”を測れているのか?」と。
彼らは、学術的に信頼されている「保育環境調査スケール(ECERS-3)」という評価ツールと、第三者評価を照らし合わせた。その結果は、ちょっとショックなものだった。
——まったく関係がなかった。
第三者評価の点数と、子どもの発育、就学後の学力、保護者の子どもへの関わり方には、なんの関連も見つからなかったのだ。
つまり、「高評価=よい保育」とは限らない。
そして、「園の違いを知るための評価」でもなかった。
では、この評価は何のためにあるのか。
本当に子どもたちのためになっているのか。
著者たちは提案する。評価項目を科学的に見直し、本当に子どもの育ちにとって意味のある内容にすること。そのうえで、信頼できる方法で評価し、公表すること。それができたとき、初めてこの仕組みは「意味ある羅針盤」として機能するはずだ、と。
🧾まとめ
保育園選びは、人生の大きな選択のひとつだ。
「高評価だから安心」と思いたくなるけれど、その評価の“中身”を、すこしだけ立ち止まって見てみることも大切かもしれない。
評価がただの「数字」ではなく、本当に子どもと保育の未来に結びつくものになるように。
私たちがすべきことは、時々立ち止まり、静かに問いかけることかもしれない。
その評価は、“本当に見るべきもの”を見せてくれているか?と。
<参考>福祉サービス第三者評価と保育の質との関連:現状と課題(独立行政法人経済産業研究所)https://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/22j042.html

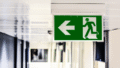
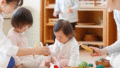
コメント