暮らしというのは、驚くほどたくさんの「小さな当たり前」でできています。朝、目覚める。顔を洗う。玄関を出て、歩いて、今日という日を始める。
そんなひとつひとつの積み重ねを、いつも通りに過ごせることが、実はかけがえのない奇跡なのだと、保育という仕事をしていると、折に触れて気づかされます。
令和6年7月10日、世田谷区の早苗保育園〈分園〉ほなみにて行われた定期の指導監査。その結果、「消火訓練が未実施の月があった」との指摘をいただきました。
この一文を読んで、驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。心配をされた方もいるでしょう。私たち自身も、深く反省しました。
それは、子どもたちの命を預かる場所として、見落としてはならない大切なことだったからです。そして同時に、それがどのような背景で起きてしまったのかを、誠実にお伝えする責任があると思いました。
この記事では、私たちが経験した「小さなほころび」について、包み隠さずにお話します。そして、それを通して見えてきた「本当に大切にしたい保育のあり方」と、保護者の方や、これから保育士として働く方にとっての「園選びの視点」についても、あわせて綴っていきたいと思います。
この文章が、どこかで誰かの気づきや安心につながることを願って。
<参考>世田谷区 指導検査について
https://www.city.setagaya.lg.jp/01044/1632.html#p4
■ 忘れてしまった「一日」の重み
私たちは、保育の現場で日々さまざまなことに取り組んでいます。
子どもたちが毎日を楽しく、安心して過ごせるように。
笑顔でいられるように。
遊びのなかで学び、心が豊かに育つように。
それはもう、目が回るほど忙しいことの連続です。朝の受け入れ、食事の準備、午睡、連絡帳の記入、保護者対応。そこに行事やイベントの準備が重なることもある。
そんななか、ある月、私たちは「消火訓練を実施する」という月例の予定を、行事や人手不足のためにいったん延期しました。代替日を設けようとしつつも、日々の忙しさに紛れて、そのまま翌月になってしまったのです。
「あとでやろう」と思ったことを、「そのうちに」と見送ってしまった。
それが、結果的に「実施できなかった月をつくってしまった」という形で、今回の監査の場で明らかになりました。
言い訳はできません。たったひと月、という気持ちがあったのかもしれません。でも、火災は「いつ起きるか分からない」のです。まさにその月に何かがあったなら——そう思うと、背筋が冷たくなる思いがしました。
■ 子どもたちにとっての「防災」は、生活そのもの
保育園における防災は、訓練という形をとって、毎月行うことが定められています。これは、ただの義務や形式ではありません。命を守る知恵を、子どもたちと大人が一緒に育む時間です。
3歳児の小さな手が、笛の音に耳を澄ませ、先生の声に従って、しっかりと避難経路を歩く。
5歳児が下の子の手を引いて、「大丈夫だよ」と声をかける。
大人が誘導するだけではなく、子どもたち自身が自分の力で「逃げる」「守る」「助ける」ことを学ぶ——それが、私たちの目指す訓練の姿です。
防災の意識は、一朝一夕では育ちません。
そして、なによりも「繰り返すこと」が、身を守るための最も確かな方法だと思うのです。
私たちはその一歩を、ある月、怠ってしまいました。
子どもたちにとって、それは「一日」が失われたことと同じです。
日常に戻れるかどうかの境界線に立たされる、その一日を軽んじてしまった。
その重さを、今あらためて感じています。
■ 誠実であるということ
今回の指摘を受け、園内で話し合いを行いました。
「なぜ実施できなかったのか」
「なぜ、リマインドが機能しなかったのか」
「再発をどう防ぐか」
意見を出し合い、時に厳しい言葉も交わしながら、全職員で共有しました。そこにあるのは「責任」ではなく「信頼」です。
誰かを責めても、未来はつくれない。
ならば、何をすべきか。
どんな小さなことも「後回しにしない」こと。
小さな声を「聞き逃さない」こと。
そして、「困っている人がいないか」を常に気にかけること。
そういう、日々の姿勢そのものが、子どもたちにとっての「安心」になるのではないかと感じています。
■ 保護者の方へ——園選びで大切にしてほしいこと
お子さまのために、保育園を探されている保護者の方に、ひとつだけお伝えしたいことがあります。
それは、「安全対策はどのようにされていますか?」という質問を、見学の際にぜひしてみてください、ということです。
もちろん、カリキュラムや行事、先生の雰囲気、食事の内容も大切です。でも、命を預ける場所として「どれだけ具体的に安全を考えているか」は、その園の“本気度”を見極める大切なポイントになります。
・避難訓練・消火訓練は毎月行われているか?
・その振り返りはどのようにしているか?
・災害時の保護者との連絡方法は?
そんな問いに対して、目を見て、まっすぐ答えてくれる園こそ、子どもたちの毎日を大切にしている場所だと私は思います。
■ 保育士の方へ——転職活動中に見てほしいもの
いま、転職を考えている保育士さんへ。
どんな園に入りたいですか?
何を大切にして、次の場所を選びますか?
条件や待遇も大事です。でも、もうひとつ、「失敗をどう扱うか」という視点を持っていただけたらと思います。
ミスが起きたとき、責任のなすり合いになる園。
問題を指摘されても、隠そうとする園。
そういった場所は、きっと、あなたの誠実さを活かせません。
むしろ、何かが起きたときに
「みんなで共有しよう」
「次に生かそう」と言える場所。
そういう文化がある園こそ、あなたの学びと挑戦を支えてくれると思います。
■ まとめ——日常という奇跡を守るために
小さなミスを誠実に受け止める。
それは、自分たちの歩幅を確かめ直すことでもあります。
今回、私たちは「一月の消火訓練ができなかった」という反省から、多くの気づきを得ました。
でも、気づいたからこそ、もう一度初心に帰り、ひとつひとつの「まいにち」をていねいに積み重ねていくつもりです。
子どもたちにとって、安全とは「気づかれない優しさ」であるべきです。
何も起きない日々を、そっと守っていること。
そのために、私たちは、見えないところで汗をかき、声をかけ合い、そして時に立ち止まりながら、歩んでいきます。
どんなに忙しい日々でも、「まいにちを大切にする」こと。
それこそが、私たち保育の原点なのです。
この文章が、誰かの心のどこかに、小さな安心として残ってくれたら嬉しく思います。
<参考>世田谷区 指導検査について
https://www.city.setagaya.lg.jp/01044/1632.html#p4


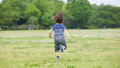
コメント