保育園を選ぶとき、何を大事にすればいいのでしょうか。子どもを預ける側の保護者も、働き先を探す保育士も、それぞれにたくさんの不安と願いを胸に抱えています。今回は、千葉県流山市の「えどがわ南流山保育園」で行われた指導監査の内容を通して、「保育園に求められる本来の姿」と「安心できる園選びのヒント」を一緒に考えてみたいと思います。
この記事でわかること
- 「自己評価」と「職員配置」に関する指導監査の指摘の背景と意味
- 子どもたちの育ちにとって、なぜこれらが大切なのか
- 保護者として保育園を選ぶときの視点
- 保育士として転職先を選ぶときのポイント
- 保育という仕事に向き合う人へのエール
小さな指摘にこめられた、大きな問いかけ
千葉県流山市の「えどがわ南流山保育園」では、令和6年11月12日に定期の指導監査が行われました。そこで指摘されたのは、以下の2点です。
- 自己評価
- 職員配置
一見すると、細かな書類の不備や、制度上の基準のように見えるかもしれません。でも、保育という営みを支える根っこの部分に、実は深く関わっている指摘でもあります。
わたしはこれを読んで、「ふりかえること」と「支えあうこと」が、今、あらためて大切にされているのだと感じました。
自己評価とは、「よりよい明日をつくる手紙」
保育園に義務付けられている「自己評価」。これは単なる自己採点ではありません。
日々の保育をふりかえり、
どんな子どもの笑顔があったか。
職員同士でどう支え合えたか。
地域との関係はどう育っているか。
そんな問いを静かに見つめ直す作業です。これをきちんと行うことで、職員全員が同じ方向を向き、保育の質を高めていくための手がかりが生まれます。
今回の監査では、この自己評価の記録や取り組みに不足が見られたようです。おそらく、忙しい日々のなかで、「ふりかえる時間」が後回しになってしまったのかもしれません。けれども、そういうときこそ、立ち止まる勇気が必要なのです。
子どもたちのために、保育士自身が「わたしたちはどうありたいか」を問いつづける姿勢。それが、良い保育の根っこになります。
職員配置とは、「安心の土台」
もうひとつの指摘が「職員配置」。これは子どもの人数に応じて、必要な人数の保育士が適切に配置されているか、という点です。
国の基準では、年齢ごとに必要な保育士の数が定められています。たとえば0歳児なら「子ども3人に対して保育士1人」など。しかし、現場は常に予測不可能。急な欠勤や、行事の準備、保護者対応、さまざまな「想定外」が毎日おきます。
そうしたとき、園全体で連携し、余裕をもって対応できる体制があるかどうか——それが、子どもたちの安全や、職員の安心につながるのです。
今回の指摘が意味するのは、「必要な場面に、必要な人手が十分だったかどうか」。園の運営が忙しさに追われるなかで、配置がやや不十分だった可能性があります。けれども、これもまた、改善のきっかけとなる大切なチェックポイントです。
保護者が見るべき「ふたつの視点」
では、保護者として保育園を選ぶとき、何を見ればよいのでしょう。私からのおすすめは、このふたつです。
① 職員同士の雰囲気を見る
玄関先や園庭で、保育士さん同士が自然に声をかけあっていたり、笑顔で子どもに寄り添っていたりする園は、配置にゆとりがあり、チームワークもよく回っています。
② 保育のふりかえりが公開されているか
園だよりやウェブサイトに「保育のふりかえり」や「改善点」が書かれている場合、それは自己評価をていねいに行っている証拠です。小さなミスも隠さず、改善につなげている園には、信頼がおけます。
転職活動中の保育士さんへ——園選びの3つのヒント
保育士として働く場所を探すときも、見ておきたいポイントがあります。
① 「自己評価」の時間が確保されているか
会議でふりかえりを行う時間があるかどうか。保育の質を高めようとする園には、必ずこの時間があります。
② 職員数に余裕があるか
シフトがギリギリでまわっていないか、有給が取れているか。これは現場の働きやすさと直結します。
③ 園長やリーダーが現場を理解しているか
トップが現場を理解し、職員の声に耳を傾けているかどうか。その姿勢が、チーム全体の空気をつくります。
いずれも、求人票には書かれていないことかもしれません。でも、面接や見学で、ぜひ自分の目と心で確かめてみてください。あなたが安心して、笑顔で子どもたちと向き合える場所は、きっとあります。
まとめ
今回の指導監査の指摘は、「ふりかえること」「支えあうこと」という、保育の本質を私たちに思い出させてくれました。
保護者も、保育士も、日々たくさんの選択をしています。
でもそのひとつひとつは、
「大切な誰かを想う」気持ちから生まれている。
そんなふうに感じています。
どうか、安心できる場所で、
子どもたちがのびのびと育ち、
保育士がいきいきと働けますように。
そして、そんな場所を一緒につくろうとする人たちを、わたしたちは応援していきたい。
保育という仕事に、日々の子育てに、心からの感謝とエールを込めて。
<参考>流山市 特定教育・保育施設等の指導監査(確認監査)



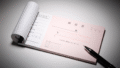
コメント