あなたが子どもを預ける保育園に、本当に信頼を寄せていますか?
保育士として働こうとしている園に、心から誇りを持てますか?
令和5年7月25日、調布市の「保恵学園保育所」に対して実施された指導監査において、「保育士の適正な配置が確認できない」という指摘がなされました。この言葉の持つ重さと、それが意味する背景には、保育の質そのものに関わる深い問いがあります。
このブログ記事では、保育士配置の基本や意義を丁寧に解説しつつ、その指摘がなぜ重要なのかを保護者の立場から、また保育士として働く方の視点からも考え直していきます。転職を検討している保育士さんには、園を見極めるためのヒントもご紹介。
すべての子どもが愛され、守られ、育まれるために。そして、すべての保育士が、その誇りを失わないために──。
この記事でわかること
- 「保育士の適正な配置が確認できない」とはどういうことか
- どんな背景でこうした問題が発生するのか
- 保育の質と配置の関係性
- 保護者が保育園を選ぶときに注目すべきポイント
- 保育士が働く園を選ぶためのヒント
- 子どもにとって、保育士にとって、本当に大切な保育とは何か
■「配置」という言葉の持つ重み
「保育士の配置が適正でない」と聞いて、どれくらいの人がその重大性に気づくでしょうか。配置とは、ただ人をそこに置くことではありません。
配置とは、子ども一人ひとりの命と成長に、どれだけのまなざしを注げるかという、保育の原点に関わる話なのです。
たとえば、国の定める基準では、0歳児3人に対して保育士1人、1~2歳児であれば6人に対して1人、3歳児以上なら20人に対して1人が配置されるべきとされています。しかしこれは“最低基準”に過ぎません。
実際の保育は、それ以上の目配りと心配りを必要とします。ミルクの温度を感じる手、泣き声のニュアンスを聴き分ける耳、そっと背中をさするあの優しい手。そうした一つひとつの行動は、適正な配置があってこそ可能になるのです。
保恵学園保育所における指摘は、つまりこの“土台”が確認できなかったということ。これは、保育の根本に対する問いかけであり、今この瞬間も保育園を探しているすべての保護者にとって、他人事ではないのです。
■なぜ、適正な配置が確認できなかったのか
一体、どのような背景があるのでしょうか。
行政の指導監査の際、「保育士のシフト表や勤務実態」「配置の記録」が適正でなければ、それは“確認できない”という評価になります。つまり、帳簿上の不備だけでなく、実態としても配置が基準を満たしていない、あるいは満たしていたとしても証明できないという状況だった可能性があるのです。
これは、保育士不足や人員配置の柔軟さを欠いた組織運営が背景にあることが多く、また、管理体制の甘さが原因であることもあります。言い換えれば、「ちゃんとしていたかもしれないけれど、記録も実態も曖昧だった」という状況では、行政は「確認できない」と判断せざるを得ません。
■子どもを中心に据えるということ
「ちゃんと見てくれているかな」
「この園に預けて大丈夫かな」
子育てをしていると、どうしても不安はつきまといます。だからこそ、保護者は保育園選びに慎重になります。
適正な保育士配置は、安心・安全の第一歩です。とくに乳児保育では、保育士との関係性がそのまま“第二の家庭”となるほど重要な意味をもちます。
保育士一人が多くの子どもを受け持っていた場合、どうしても細かなサインを見落としがちになります。体調の変化、小さなケガ、泣き方の違い──それらにすぐ気づくためには、十分な人手と、丁寧な配置が不可欠なのです。
■保護者に伝えたい、園選びの5つの視点
では、実際に保育園を選ぶとき、どこに注目すれば良いのでしょうか。以下の5つのポイントを意識してみてください。
- 保育士の人数と配置状況
見学の際に、「今日は何人の保育士さんがいて、何人の子どもを見ていますか?」と聞いてみましょう。 - シフト表や勤務体制の説明ができるか
運営体制を丁寧に説明できる園は、信頼できます。 - 保育士の様子を観察する
余裕がある様子か、慌ただしくしていないか。笑顔があるかどうかも大切なサインです。 - 保護者への説明責任を果たしているか
保育内容や一日の流れを分かりやすく開示している園は、透明性が高い証拠です。 - 監査結果や第三者評価を確認する
各自治体のホームページには監査結果が公開されています。ぜひチェックしてみてください。
■保育士に届けたい、園選びの“まなざし”
保育士として働く皆さんにとっても、配置のあり方はとても大切です。配置が不十分な園では、休憩すらまともに取れず、無理なシフトが常態化し、心も体もすり減っていきます。
自分の働く環境を守ることは、子どものためにもなります。転職活動の際には、こんなポイントを見てください。
- 面接で「配置基準」や「シフトの組み方」についてしっかり質問する
- 見学時に保育士同士の声かけや関係性を見る
- 定着率の高さを確認する(長く勤めている職員が多いか)
一緒に働く仲間を大切にし、過剰な負担を防ぐ仕組みを整えている園は、必ず保育士に優しいだけでなく、子どもにもやさしいのです。
まとめ:「手を取りあって、保育を育てる」
保育士配置という一見地味な指摘。その奥には、「保育の本質」が隠されています。何人の子どもを、どれだけの手と目で見守るのか。それは、子どもの成長の土台であり、保育士の誇りを守る要です。
保育は、目に見えにくい仕事です。でも、そのぬくもりは確かに存在し、子どもたちの未来に静かに、けれど力強く影響を与えています。
保護者も、保育士も、どうか“気づく人”であってください。見えないところに目をこらし、手のひらにある優しさを信じてください。
保育とは、人が人を想い、支えあうこと。
その想いが、今日もどこかの園で静かに息づいていることを願って──。
<参考>調布市 特定教育・保育施設の指導検査
https://www.city.chofu.lg.jp/050010/p027027.html


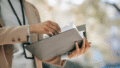
コメント