朝の光が、まだうっすらと眠たそうな街に差し込む頃、ある家庭では、小さなリュックを背負った子どもが「きょうはほいくえん?」と母の手をぎゅっと握ります。その一方で、別の家庭では、保育園の利用申し込みに落選した通知を握りしめながら、祖母に子どもを預けて出勤する親がいます。
そんな日常が、全国で静かに、けれど確かに繰り返されています。
令和六年四月の「待機児童数調査」が公表されました。数字として見れば、「2,567人」という結果。前年度から113人減りました。国の政策が一定の効果を上げている証拠とも言えるかもしれません。
しかし、私たちはこの「2,567人」という数を、単なる統計として受け取ってはいけないと思うのです。なぜなら、その一人ひとりには名前があり、生活があり、そして未来があるからです。
数字の向こう側にある、静かな願い
報告書によれば、全国の約87.5%の市区町村、つまり1,524もの自治体では待機児童が「ゼロ」でした。これは素晴らしい成果です。行政の努力、保育現場の尽力、そして地域社会の連携が積み重ねた結果でしょう。
けれども、待機児童が50人以上いる自治体は、依然として6つあります。この「6」という数が、去年から減っていないという事実に、私は小さな警鐘を感じます。
保育所が足りない、保育士がいない、急な転入や宅地開発で想定を上回る申し込みが殺到する──理由はさまざまです。しかし、根っこにあるのは、どの家庭も「子どもを安心して預け、働きたい」というまっすぐな願いです。
その願いが、時に叶わず、家族の働き方や暮らし方にまで影響を及ぼしていることを、私たちは忘れてはいけません。
減少と増加──複雑に絡み合う現実
「待機児童が減った地域」と「増えた地域」。この二つの動きが同時に起きているのが、今の日本の保育をめぐる現実です。
たとえば、出生数が減り、保育ニーズそのものが減少している地域では、保育所の空きが目立つようになってきています。ここでは、待機児童は自然と減少します。
一方で、都市部や人口流入の多い地域では、申し込みが想定以上に増え、結果として定員が足りなくなる。加えて、保育士の確保が困難で、施設が定員どおりに運営できず、結果的に「受け皿はあっても使えない」という状況が生まれています。
このように、同じ「日本」という国の中でも、地域ごとにまったく違う風景が広がっているのです。
保育の本質は「誰かを大切にする」こと
かつて、ある保育園の園長先生がこうおっしゃいました。
「保育というのは、子どもを預かることではなく、その子の未来をいっしょに育てることなんです。」
この言葉が、今でも私の心に強く残っています。
保育士という職業は、単なる労働ではありません。日々の営みのなかで、子どもたちの心に種をまき、水をやり、陽を注ぐ。その先にある芽吹きや成長を、時間をかけて見守る。そんな尊い仕事です。
だからこそ、保育士が足りないという現実は、私たち社会全体にとっての課題です。給与の問題、働き方の問題、人材育成の問題。ひとつずつ丁寧に向き合わなければ、どれだけ施設数を増やしても、本当の意味での「待機児童ゼロ」は実現しないのではないでしょうか。
変わりゆく社会、変わらぬ願い
女性の就業率は、令和4年の79.8%から、令和5年には80.8%へと上昇しました。共働き世帯も73.7%から75.6%へと増えています。
社会が変わり、家庭の在り方が変わり、働くということの意味が変わりつつある今、保育という営みの持つ役割はますます大きくなっているのだと思います。
保育は、ただの「支援」ではなく、社会の「インフラ」であり、「文化」でもある──私はそう信じています。
これからの保育に求められること
今回の調査で見えてきたのは、「数」だけを追い求める時代の終わりと、「質」と「持続可能性」を考える時代の始まりです。
これからの保育に必要なのは、次のような視点でしょう。
- 保育士が安心して働ける職場環境
- 地域ごとの保育ニーズに応じた柔軟な政策
- 子ども一人ひとりの特性に配慮した支援体制
- 多様な保育形態(夜間保育、病児保育、一時保育など)への対応
どれも一朝一夕に実現できるものではありません。しかし、私たち一人ひとりが「自分ごと」として考え、行動していくことで、少しずつ社会は変わっていくはずです。
園運営者の皆さまへ──「まもる」から「そだてる」へのまなざし
この国で、保育に携わるということは、社会の最前線に立つということです。
たとえば、早朝。まだ街が眠っている時間に園を開けるという決断。寒い日も、雨の日も、保育士が安心して働けるようにと、こまやかに目を配る姿勢。あるいは、予期せぬ欠員や急な保護者対応に奔走しながらも、「今日も子どもたちは笑っているか」を常に気にかける心。
それは経営という名の仕事を超えて、人の営みそのものです。
今回の待機児童数の発表には、ただの統計ではない「現場からの声」が刻まれていると、私は思います。施設数を増やせば解決する話ではなく、人を育て、環境を整え、ひとつひとつの保育の質を守る努力が、これまで以上に求められています。
特に保育士不足の問題は、全国の園で深刻さを増しています。「求人を出しても応募が来ない」「若手がすぐに辞めてしまう」「ベテランが疲弊している」──そんな声が、各地から聞こえてきます。
けれど、私たちはこう考えてみることもできるのではないでしょうか。
保育園とは、ただ子どもを預かる場所ではなく、地域に根を張った「暮らしの交差点」である。保育士とは、子どもと家族と地域をつなぐ「懸け橋」である。
その原点に立ち返りながら、運営のあり方を問い直すとき、こんな問いが浮かび上がってきます。
- 私たちの園は、子どもにとって「帰ってきたくなる場所」になっているか?
- 働く職員にとって、「ここで働きつづけたい」と思える園だろうか?
- 保護者にとって、「この園に出会えてよかった」と心から感じてもらえるか?
答えは一つではありません。しかし、その問いを持ち続ける姿勢こそが、これからの園運営の指針になるのだと私は信じています。
また、保育の質を高めるためには、園内だけで完結せず、地域や行政との連携が欠かせません。情報を共有し、相談し合い、時には課題をともに担う。そうした「つながり」の中にこそ、保育の持続可能性があるのではないでしょうか。
令和六年の待機児童数「2,567人」。
この数字の中には、保護者の戸惑いだけでなく、運営者としての皆さまの葛藤や苦悩も含まれているはずです。
それでも、なお。朝、子どもが園の門をくぐるとき、「おはよう」と笑顔で迎える職員の姿がある限り、この国の保育は守られているのだと、私は信じたい。
どうか、これからも。どうか、あの子の未来のために。
運営という大きな責任の中で、みずからを律しながらも、「やさしさ」と「まなざし」を忘れないでいてください。
園は、社会の未来を育てる場所です。
そして運営者は、子どもたちの「安心」を照らす灯台なのです。
終わりに──「たったひとり」を大切にする社会へ
数字は大切です。統計は政策の舵をとるために不可欠な道具です。
けれども、私たちが本当に大切にしなければならないのは、「その数字のひとつひとつが、ひとりの子どもである」という事実です。
令和六年の春、2,567人の子どもが、希望する保育所に入れませんでした。
そのうちのひとりが、あなたのご近所にいるかもしれません。あるいは、あなた自身の子どもだったかもしれません。
だからこそ、私たちは声を上げ続けたいのです。
すべての子どもに、愛と安心に満ちた保育が届きますように。
すべての親に、働く喜びと、育てる誇りが与えられますように。
そしてすべての保育士に、心からの感謝と尊敬が届けられますように。
その願いを胸に、私はこの数字と静かに向き合い、考え続けたいと思います。
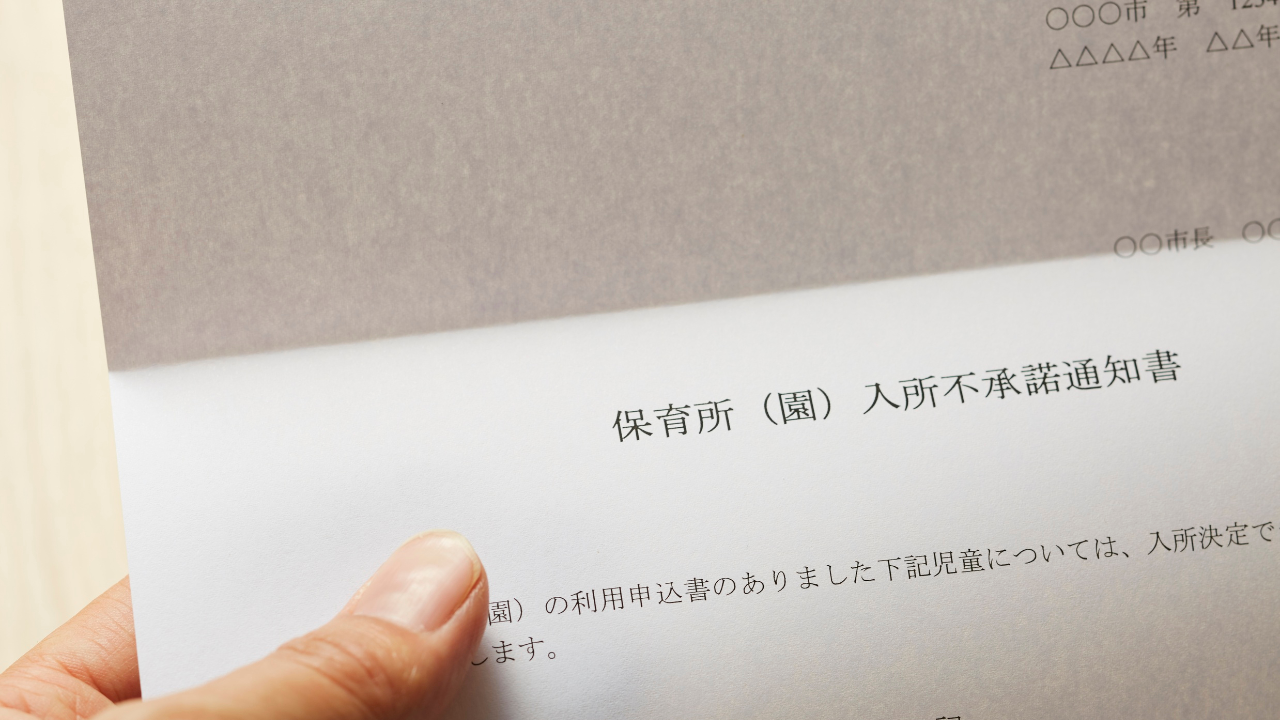


コメント