保育園――それは子どもたちが初めて社会と出会う場所であり、親たちが心を託す居場所であり、保育士たちが夢と現実のはざまで日々戦う職場でもある。だがその現場において、船の舵を握るべき船長が、実は別の船にも乗っていたとしたらどうだろう?江戸川区・AIAI NURSERY 西小岩の監査結果から、いま保育園に求められている「リーダーシップのかたち」を考える。
この記事でわかること
- 「施設長専任」の意味とその必要性
- なぜ“兼務”が問題とされるのか
- 保育園の組織運営における施設長の役割
- 保護者が保育園選びで注視すべきポイント
- 保育士が転職活動で確認すべき園の運営体制
「保育園の園長って、普段何してるの?」
そんな質問を受けたのは、もう何年前になるだろうか。保育者としての経験を持ち、いまも保育現場に関わる身として、この問いは、少し寂しさと、少し怒りと、でも何よりも誤解をはらむ危うさを感じる。
園長は、いる。だが、見えない存在になってしまっている園もある。それは、単に姿を現さないということではない。――その存在感が、現場で機能していないのだ。
令和6年10月3日、江戸川区の「AIAI NURSERY 西小岩」において実施された行政監査では、「施設長が専任でない」という指摘がなされた。これは、園長職にある者が当該施設以外の業務に就いていた、あるいは複数園を兼務していた可能性を意味している。
制度上、「専任」であることは法律に定められた義務である。児童福祉法、そして東京都の保育所設置運営基準では、施設長はその保育所に常駐し、運営・保育・安全管理を指揮することが求められている。
では、なぜそれが守られていなかったのか。
■“兼務”の背景にある現場の人材不足
現場を知る者としては、その事情も痛いほど分かる。人材がいないのだ。保育士も足りない、主任格の職員も不足している。そして法人としては、急増する保育需要に応えるべく園を増やし、体制を整える暇もなく次の園の開設が待っている。
こうした中で、法人本部は“やりくり”をせざるを得なくなる。新園が開園したが施設長が決まらない。ならば既存園の園長が兼務すればよい。行政との折衝も済んでいる、書類も一時的ならと目をつぶってもらえる。……そんな“暫定”が、いつの間にか“恒常”になっていく。
だがそれは、決定的な穴を開ける。園の屋台骨を支えるべき「施設長」の空洞化である。
■保育園の“舵取り役”がいないリスク
園長は、ただの名義上の責任者ではない。彼/彼女は、園という小さな社会の“船長”だ。日々起こる問題――保護者との行き違い、職員間の衝突、子ども同士のケンカ、虐待の芽、安全事故――こうした一つひとつに対応し、保育士たちを守り、支え、方向性を示すのが施設長の仕事である。
その施設長が“いない”園は、まるで荒れた海を漂う小舟のようなものだ。舵がないまま、職員が右往左往し、保護者も不安を抱え、子どもたちはその雰囲気に敏感に反応する。――何よりも、一人ひとりの保育士が疲弊していく。
「なんで私たちばっかり頑張ってるんだろう?」
そんな声が出るようになったら、組織としては危ない。
これはAIAI NURSERY 西小岩だけの話ではない。都市部の急速な保育園拡大の影で、同じような構造的問題を抱える園は少なくない。
■保護者が見るべき「園の顔」としての園長
では、私たち保護者はどうすればよいのか。
「園長先生に会わせてください」
――これは、入園前の面談や見学時にぜひ言ってほしい一言である。園長が専任かどうかは、その応対でわかる。「今日は不在です」「別園におります」……そんな返事が返ってくるなら、少し立ち止まって考えた方がいい。
子どもの命を預けるのに、園の“指揮官”がそこに常駐していない。これは、車に乗るときにハンドルがついていないようなものだ。
園長がどれだけ現場に目を向け、子どもたちの名前を覚えていて、保育士に声をかけているか。そこを見てほしい。そして、そうした姿がない園であれば、いくらきらびやかなパンフレットや最新の設備が整っていても、その“核”がない可能性があるのだ。
■保育士が「園選び」で見ておくべきこと
転職活動中の保育士にとっても、施設長の在り方は極めて重要である。
まず確認してほしいのは、園長が毎日園にいるかどうか。
そして、園長と職員の距離感。
・主任や中堅保育士が気軽に園長に声をかけているか
・書類のやりとりだけで会話がないような関係性になっていないか
・困ったとき、相談できる風土があるか
また、法人全体の姿勢にも目を向けたい。
・「兼務」や「名義上だけの配置」が蔓延していないか
・人材育成のための時間と資源が確保されているか
・園長を「経営管理者」ではなく「保育のリーダー」として育てようとしているか
こうしたことは、面接の際や見学時に質問してみてほしい。
「施設長は、今この園に常駐していますか?」
「園長先生は、子どもの日々の様子にどのくらい関わっていますか?」
それだけで、その法人の保育への向き合い方が透けて見えるはずだ。
まとめ:「園長がいる」ことの重みと、私たちが選ぶ力
保育園は、建物やおもちゃ、きれいなパンフレットで決まる場所ではない。そこに“魂”を宿しているのは、「人」であり、なかでも“園長”という存在が中心にいるかどうかが、その園のすべてを決めるといっても過言ではない。
専任の施設長がいないということは、つまりその園における“保育の司令塔”が不在ということだ。子どもたちの育ち、保育士たちの苦労、保護者の不安――それらすべての“受け皿”がないという現実を、私たちはもっと真剣に捉えなければならない。
現場で踏ん張っている保育士たちには、心から「ありがとう」を言いたい。そして、これから保育を志す人、いまの職場に迷いを感じている人には、自らの働く環境を見つめ直し、“安心して任せられる園長”のいる場所を探してほしい。
保護者としては、どうか“園長に会ってください”。その一言が、わが子の未来を守る小さな一歩になる。
そして私たちは――選ぶことができる。
不在の園長ではなく、“そこにいる”園長を。
誰かのためではなく、子どもたちのために、今日も一歩前へ。
<参考>江戸川区 検査結果
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e047/kosodate/kosodate/kensa/kekka.html

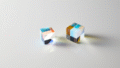

コメント