ある日、ふと目にしたニュースに、私は立ち止まりました。令和6年11月、品川区のソラストひがしおおい保育園で行われた指導監査で、「保育士の適正配置がなされていない」という指摘があったというのです。
その言葉だけを見ると、なんだか難しく、少し遠い世界のことのように感じるかもしれません。でも実は、ここに暮らす私たち一人ひとり、そして子どもたちの未来に、深く関わるとても大事な話なのです。
今日はこの出来事を入り口に、保育とは何か、保育園とはどんな場所であるべきか、そして保育士として働くことの意味を、静かに、でもしっかりと見つめ直してみたいと思います。
これは、保育園を探しているお父さんお母さんへ。そして、新たな職場を探している保育士の皆さんへ。さらには、日々の暮らしの中で「やさしさとは何か」を考えるすべての人へ向けた、小さな手紙のような文章です。
この文章でわかること
- 保育士の「適正配置」とは何か
- 今回の指摘が意味する背景と影響
- 保育園選びで大切にしたい「やさしさの基準」
- 保育士として、園を選ぶときに見つめるべき心のポイント
- 子育てと保育の間で、頑張るあなたを応援する言葉
たった一言の指摘から見えてくるもの
保育園に子どもを預ける。
言葉にすると、たったそれだけのことのように思えるかもしれません。
でも、そこには「信頼」があります。朝、子どもを送り出すとき、「今日もこの場所なら大丈夫」と心から思えるかどうか。それは、親としての暮らしの中でもっとも大きな安心であり、もっとも大きな願いでもあります。
そんな中で耳にした、「保育士が適正に配置されていない」という言葉。これは、その信頼の根っこに、小さなぐらつきがあるかもしれない、というサインでもあるのです。
適正配置とは、「ちゃんとその子を見ているか」ということ
保育士の「配置」と聞くと、なんだか事務的な印象を持つ方もいらっしゃるかもしれません。でも、これはとても人間的な、そして思いやりに満ちた考え方です。
たとえば、一歳の子と、五歳の子では、必要な配慮がまったく異なります。泣いたときの抱き方も違えば、遊びたい気持ちのかたちも違う。その違いに気づき、寄り添い、その子にとっての“ちょうどいい”を見つけていくためには、適切な数の保育士、そして経験や知識を持った人が、その場にいてくれる必要があります。
それが「適正配置」です。
今回の指導監査で指摘されたのは、たとえば本来配置されるべき保育士の人数に足りていなかったり、保育士資格を持たない補助スタッフに頼りすぎていたりといった、不安定な人員配置だったと考えられます。
こうした状況では、急なトラブルや体調の変化に柔軟に対応できないこともあります。保育は、日々、何が起こるかわからない生きた時間です。だからこそ、予測不能な「もしも」に備えて、「ちゃんと見てくれている人がいる」ことが、なによりも大切なのです。
どうしてこんなことが起こったのか
これは誰か一人の責任ではありません。
日本全国、保育士不足が深刻です。待遇が厳しく、働きながら自分の生活を守ることが難しい。心を尽くしても報われないと感じてしまう現場が、まだたくさんあるのです。
園長先生も、現場の先生も、皆さんぎりぎりのところで頑張っておられます。人手が足りない中で、子どもたちの笑顔を守ろうと、毎日工夫を重ねている。指摘を受けたからといって、それがすぐ「悪い園」というわけではないことも、忘れずにいたいのです。
むしろ、今回のように指摘を受け、改善に取り組もうとする姿勢こそが、未来の保育に希望を灯してくれるはずです。
保育園を選ぶときに、大切にしたい“たったひとつのこと”
保護者として、保育園を選ぶとき。設備の新しさ、立地の便利さ、見た目の明るさ……いろんな基準があります。
けれど、もっとも大切にしたいのは、「ここで働いている人たちは、子どもを大切にしているか?」ということです。
見学のときには、ぜひ先生たちの表情を見てください。忙しい中でも子どもに目を配り、声をかけ、やさしく背中をさすっている先生がいますか? 子どもたちが笑顔で、安心して過ごしている空間ですか?
どんなに完璧に見える園でも、先生たちの心が疲れていたら、それはきっと子どもにも伝わります。逆に、設備が多少古くても、先生たちがいきいきと働いていたら、その園はきっと信頼できる場所です。
選ぶ基準は、「やさしさ」です。
転職活動中の保育士さんへ──選ぶことは、諦めないこと
もし今、あなたが保育士として次の職場を探しているなら、自分を責めないでください。
どんなに子どもが好きでも、心がすり減ってしまう職場では続けられません。あなたが笑っていられない保育は、きっと誰かにとっても苦しい保育になってしまう。だから、どうか自分自身を大切にする選択をしてください。
保育園を選ぶとき、「ここなら、私も大切にされそう」と思える園を見つけてください。園長先生の言葉に誠実さがありますか? 職員同士の空気は、穏やかですか? 子どもたちが、のびのびと育っていますか?
誰かのために働くために、まずは自分が幸せであること。それは、決してわがままではありません。
おわりに──保育は、「信じる」ということ
保育という営みは、ただ子どもを預かるということではありません。
それは、子どもを信じ、保護者を信じ、仲間を信じ、自分を信じるという営みです。
今回の指摘を通じて、私たちは改めて、「信じられる環境」をつくることの大切さを知りました。人手が足りないとき、忙しさに追われて見失いそうになるその瞬間こそ、大切なのは“目の前の子どもに、ちゃんと心を向ける”こと。
やさしさは、いつも見えないところに根を張っています。保育園選びも、職場選びも、「やさしさが根づいているか」を確かめる行為です。
この文章が、誰かの心に、小さなやさしさの灯をともせたなら──
それが、私にとっての喜びです。
<参考>品川区 指導検査について
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-hoyou/hpg000033487.html


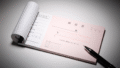
コメント