子ども一人ひとりの「違い」に、わたしたちはどこまで目を向けているでしょうか。
2023年6月、横浜市鶴見区のみつばち保育園で行われた指導監査で、「障害のある子どもへの支援計画が個別に作成されていなかった」という指摘がありました。
この出来事をきっかけに、保護者として、また保育士として、あらためて保育の本質を見つめなおすことができたらと思うのです。
この記事では、その背景にある構造的な問題をひもときながら、「本当にあるべき保育」と「働く保育士が園を選ぶときの大切な視点」をお届けします。
この記事でわかること
- 指摘事項「支援計画未作成」はなぜ起きたのか
- 障害のある子どもに必要な支援計画とは何か
- 理想的なインクルーシブ保育のあり方
- 保護者として園を選ぶ際のヒント
- 転職を考える保育士に向けた園の見極めポイント
■ 「気づかなかった」ということは、罪ではない。でも、責任はある
監査の指摘には事務的な響きがあるかもしれません。
「支援のための個別計画が作成されていなかった」。
ただの“書類不備”のように見えるかもしれませんが、それは違います。
これは、そこにいるひとりの子ども、つまり「名前のある誰か」が、その子にとって最適な育ちの場を得られていなかった可能性があるということ。
つまり、「その子の個性に寄り添う対話の場がなかった」ことなのです。
個別の支援計画とは、単なる書類ではありません。
保育者がその子を理解しようとする姿勢であり、
園として「その子に必要な支援とは何か」を丁寧に積み上げる行為であり、
なにより、子ども自身が安心して過ごすための橋です。
■ どうして「個別支援計画」が作成されなかったのか
ここには、いくつかの構造的な背景が考えられます。
- 人手不足
現場は、常に時間との戦いです。
特に都市部の私立園では、保育士が足りず、配置基準ギリギリでまわしている場合も少なくありません。
日々の保育に追われ、個別の支援計画にまで手が回らなかったのかもしれません。 - 理解の不十分さ
障害のある子どもを受け入れることはできても、具体的にどのような配慮や支援が必要かが職員全体で共有されていなかった可能性もあります。
「診断名があるから」「医療的なケアが必要ないから」という判断で、「特別な支援は不要」と誤解されることも。 - 制度上の隙間
実は、障害児保育の支援計画は「義務」とまではされていない自治体もあります。
しかし、書かれていないからといって、「やらなくてもよい」わけではありません。
むしろ、書かれていないからこそ、「やるかやらないか」の差が、保育の質を大きく左右するのです。
■ 本来、保育は「違い」を愛する営みである
子どもたちは、みんなちがいます。
背の高さ、声の大きさ、得意なこと、苦手なこと。
話せる子もいれば、沈黙の中で気持ちを伝える子もいます。
私たち大人がするべきことは、「ちがいをなくすこと」ではありません。
それぞれの子の「ちがい」に気づき、「その子らしさ」を生かせる環境をつくることです。
障害がある子どももそう。
その子にはその子の世界の捉え方があり、リズムがあり、表現の仕方があります。
個別支援計画は、その子のリズムに耳を澄ませ、
「どうすればこの子が笑顔でいられるか?」を、
複数の大人が一緒になって考えるための地図のようなもの。
書かれるべきなのは「できること」と「困っていること」だけではありません。
「どんなときに目を輝かせるのか」「どんな遊びが好きか」
その子の大切な宝物を記す、愛の記録なのです。
■ 保護者の方へ──園を選ぶときの見えない視点
保活という言葉があるように、いま、保護者が保育園を選ぶ時代です。
見学や面接で、いくつもの園を回る方もいらっしゃるでしょう。
そこで、ひとつだけ見てほしいものがあります。
「この園は、子どもの違いをどう捉えているか?」
質問してみてください。
「障害のあるお子さんへの対応は、どうされていますか?」
本当にインクルーシブな園であれば、たとえ診断名がなくても、
「ひとりひとりに応じた保育を心がけています」と語ってくれるでしょう。
支援計画の有無や、保護者との連携のあり方を、
丁寧に教えてくれるかどうか──それが、園の“まなざし”を表しています。
■ 転職を考える保育士の方へ──園を選ぶポイント
保育士として転職を考えるとき、つい「給与」や「勤務時間」ばかりに目がいきがちです。
もちろん、それも大切。
でも、長く働き続けられる園には、もうひとつ大切なことがあります。
それは、「子どもの違いに目を向けているか?」です。
たとえば、園内研修にどんなテーマが取り上げられているか。
障害児保育やインクルーシブ教育の視点があるか。
多様な背景の家庭とどう関わっているか。
そして何より、
「この子にとってのしあわせとは何か?」を語り合える仲間がいるかどうか。
書類が整っているかよりも、
保育日誌が美しいかよりも、
「この子にとって、今日がどんな日だったか」を語れる場のある園を、
どうか選んでください。
まとめ
保育とは、社会の中のいちばん小さな希望です。
わたしたちは、子どもたちの「ちがい」を恐れるのではなく、
その光を受けとめる器でありたい。
みつばち保育園の指導監査を受けて、
それが“ダメな園”なのでは決してありません。
むしろ、これを機に変わっていける機会を得たということです。
保育の道にかかわるすべての人へ。
そして、子どもを預ける親たちへ。
今日という一日が、
子どもをまんなかにおいた、やさしい対話で彩られるように──
そう願いながら、この記事を届けます。
<参考>横浜市 指導監査結果https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/ninka/kanendokekka.html

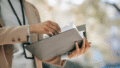

コメント