こんにちは。
もし、いま、あなたが子育て中で、保育園を探していたり、あるいは保育という仕事に関わっていたりするならば、今日の話が、ほんの少しでも参考になればと思いながら、これを書いています。
2024年の秋、東京・品川区にある保育園で、ひとつの出来事がありました。
行政の定期的な監査において、その園では「3歳未満児に提供する食事を、施設内で調理していなかった」という指摘がなされたのです。
それは一見、とても些細なように思える報告かもしれません。
でも、私はこの一文を読んだとき、ふと、胸がすうっと冷たくなるような、そんな気がしました。
なぜだろう。
そう考えていくうちに、あらためて「ごはんとは、なんだろう」「保育とは、どうあるべきなんだろう」と思い巡らせたのです。
ですから今日は、「保育園の食事」という、あまり普段は意識されにくいことについて、ひとつのエッセイとしてお届けしてみようと思います。
食事とは「つながり」である
まず、結論から申し上げます。
保育園において、ごはんがその場でつくられているということは、
子どもにとって「安心」の土台であり、保育そのものの大切な一部なのだと、私は思っています。
3歳未満の子どもたちは、言葉でうまく気持ちを伝えられません。
自分が空腹かどうかも、時にはわからない。食べ物の好き嫌いも、味の好みも、日によって変わる。
それでも、そんな子どもたちが日々、育ち、笑い、食べ、生きていくのは、「いま、ここにいる私を見てくれている大人」がいるからです。
今日の体調はどうか。昨日、苦手そうにしていた食材はどうしようか。口に入れた瞬間の反応は? 食べるペースは?
それらを見守りながら、目の前のひとりに寄り添って、すこしずつ、ほんとうに少しずつ、世界とつながる練習をしていく。
その営みを支えるのが、「その場でつくられたごはん」なのです。
炊きたてのごはん。やさしく煮込まれた野菜。
小さな手で触れたときの温度、口に入れたときのやわらかさ。
そして、食べながら聞こえてくる音――スプーンが器に触れる音、先生の声、まわりの友達の笑い声。
それらすべてが、子どもたちにとっての「日常の風景」であり、心の居場所になります。
ごはんは、ただお腹を満たすだけのものではありません。
ごはんとは、ひととひとの「つながり」そのものである。
私はそう思います。
指摘された「調理なし」の保育園で起きていること
今回、品川区で指摘された保育園では、施設の中で食事が調理されていなかった。
代わりに、外部の業者が調理したものを、運び込んで提供していたそうです。
もちろん、そうした方法にもメリットはあるのかもしれません。
食中毒のリスクを減らす、調理人材の確保が難しい、設備投資が不要になるなど、現実的な理由があるのでしょう。
でも、それでも私は、保育園という場所が「暮らしの場」であることを考えると、やはり、その場でつくることの意味を失ってはいけないのではないか、と感じます。
たとえば、あたたかいスープの湯気がふわっと上がるとき。
それを目にしただけで、子どもの目がぱっと輝いたり、手を伸ばしたりする。
その反応を見ながら、「今日はお腹がすいてるね」「少しだけにしようか?」と、やりとりが生まれる。
そこには、言葉ではない“対話”があります。
外で作られたパックの食事では、その対話の芽が育ちにくい。
なぜなら、「変更」ができないからです。
今日のその子に合った味つけやかたさに、臨機応変に応えることができない。
それは、目の前のひとりひとりを「人」として見なくなる危うさに、つながっていきます。
これは、けっして保育園や先生たちが悪いという話ではありません。
むしろ、彼らもまた、「制度」と「現場」のあいだで、苦しい選択を迫られているのです。
けれど、だからこそ、私たちは、あらためて問い直さなければいけません。
「このやり方で、本当に子どもたちを見守ることができているのか?」と。
保育士のあなたへ。「園を選ぶ」ことは「自分を大切にする」こと
もし、あなたが保育士として、いま園を変えようと考えているなら。
求人票に書いてある条件や理念だけでなく、もう少し、深いところまで目を向けてほしいと思います。
おすすめしたいのは、「お昼の時間に見学する」ことです。
保育園の本質は、給食の時間にあらわれます。
子どもたちは、どんなふうに食事に向かっているのか。
先生たちは、どんな声かけをしているのか。
ごはんは、ちゃんと湯気が立っているか。
それとも、パックをあたためて出しているだけか。
調理室には人がいるか。
先生と調理員さんが、言葉を交わしているか。
アレルギーへの対応は、どうなっているか。
献立は、子どもたちの表情から更新されているか。
そうしたひとつひとつの場面に、保育園という場所がどれだけ“ひと”を大事にしているかが、見えてきます。
そしてそれは、つまり「あなたが、ちゃんと大切にされる職場かどうか」を知る手がかりにもなります。
保育とは、やさしさを与え続ける仕事です。
だからこそ、あなた自身が、やさしくされる場所でなければ、続けていくのはむずかしい。
どうか、あなたの心が安心できる場所を、選んでください。
保護者のあなたへ。「迷うこと」は、まちがっていないということ
保育園を選ぶというのは、実に難しいことです。
認可か無認可か。家からの距離。勤務先へのアクセス。空き状況。評判。
調べることが多すぎて、もう「どれが正解かわからない」と感じている方も多いかもしれません。
でも、迷うということは、あなたが子どもにとっての“本当の良さ”を考えようとしている証拠です。
あなたはまちがっていません。
ただひとつ、園を選ぶときに心に留めてほしいことがあります。
それは、「この子は、ここでどんなごはんを食べるだろうか」と想像することです。
炊きたてのごはんがあるかどうか。
野菜がどんな風に切られているか。
先生たちが子どもと食卓を囲んでいるかどうか。
それらが、“暮らし”のある園の証です。
保育園とは、育てるための施設ではなく、暮らす場所なのです。
そこに「日常のしあわせ」があるかどうか。
それが、子どもの未来をやさしく育ててくれるはずです。
おわりに――やさしい社会は、湯気のある食卓から始まる
最後に、私がいちばん伝えたかったことを、あらためて書きます。
「湯気のある保育園」は、いい園です。
それは、調理器具や厨房の設備が立派という意味ではありません。
目の前の子どもを、きちんと“人として”見つめている証だからです。
あたたかい食事がある場所には、やさしい気持ちが流れています。
そのやさしさは、子どもの心に届き、
保護者の安心をつくり、
保育士の誇りを支え、
ゆっくりと社会を育てていきます。
もしあなたが、今日この文章を読んで、「ほんのすこしだけでも、心が軽くなった」と感じてくれたなら、私はとてもうれしいです。
これからも、暮らしにまつわるあたたかな話を、丁寧に書き綴っていきたいと思っています。
どうぞ、やさしい毎日を。
<参考>品川区 指導検査について
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-hoyou/hpg000033487.html


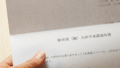
コメント