子どもを預ける場所、保育園。そこには目に見える安心と、目には見えない信頼があります。
私たちはつい、目に見えるものに頼ってしまいます。園の建物が新しいかどうか、先生の笑顔、壁に貼られた子どもたちの作品――。
しかし、本当に大切なことは、目に見えないところにあるのかもしれません。
令和6年11月28日。世田谷区のGakkenほいくえん砧で、行政による定期的な監査が行われました。
保護者に直接関係する話ではないように思われるかもしれません。
ですが、これは保護者にとっても、そして保育士を目指す人にとっても、未来を選ぶための小さなヒントを与えてくれる出来事なのです。
この記事でわかること
- Gakkenほいくえん砧で実際にあった監査指摘の内容
- その背景にある、保育園が守るべき運営のルール
- 保育園選びにおいて「透明性」が意味するもの
- 保育士として働く場所を選ぶときに大切にしたい視点
監査という“定期検診”
世田谷区にあるGakkenほいくえん砧。この園は、株式会社学研ココファン・ナーサリーが運営する保育施設であり、認可保育園として地域の多くの家庭を支えています。
行政による保育園の監査は、保育の質と園の運営が適正であるかを確認するために、毎年もしくは数年おきに行われます。これは保育園にとって言うなれば“定期検診”のようなもので、子どもたちの育ちを支える環境が健やかであるかを、第三者の目でチェックする重要な機会です。
令和6年11月28日に実施されたGakkenほいくえん砧の監査では、3つの指摘がありました。
- 必要な附属明細書が未作成だったこと
- 現金出納の処理が適正に行われていなかったこと
- 拠点区分間の資金移動において適正な処理がなされていなかったこと
これだけを聞くと、どれも会計や事務処理に関する、保護者にとっては少し縁遠く感じられる話かもしれません。しかし、それは本当にそうでしょうか。
「お金」は、保育の“いのち”を守る仕組みである
附属明細書とは、園に支給される公的資金――つまり、税金がどのように使われたかを具体的に記録するための書類です。園児1人あたりに配分される補助金や給食費、保育料。それらが何に使われたのか、きちんと書き記し、残しておくことが求められます。
現金出納とは、日々のお金の出し入れの記録のこと。たとえばおやつの材料を買った、絵本を購入した、先生方のお茶を買った。そういった細かな出費も含めて、いつ・誰が・何に・いくら使ったのかを記録し、証拠を残しておくのが正しい処理です。
拠点区分間の資金移動――これは、同じ法人が運営する他の保育園とお金のやり取りが発生する場合、その流れが適正かどうかを指します。たとえばA園のお金でB園の備品を購入するようなことがあってはいけません。
これらはすべて、透明性を保つための手続きであり、「子どもの育ちの場を健全に守る」という一点のためにあるルールです。
見えないところにこそ、本当の“信頼”がある
たとえば、あなたがレストランに入ったとします。
料理が美味しく、店員さんが感じよく、お店も清潔で、値段も手頃だったとします。
けれど、厨房が不衛生であったり、従業員の給与が未払いだったら?
それでも、そのレストランを「また来たい」と思えるでしょうか。
保育園も同じです。
見えるところ――保育室の環境や先生の笑顔――が素晴らしくても、見えないところ――お金の管理や経営の透明性――が乱れていれば、その場は長く続きません。
やがて、影響は保育士の待遇やモチベーションに現れ、子どもたちにも少しずつ伝わってしまう。そうした事例を、私たちは過去に何度も見てきました。
今回の監査指摘は、そうなる前に「きちんと立て直してくださいね」と声をかける、いわば親切なブレーキです。
運営法人が真摯に受け止め、改善を行えば、それはむしろ信頼を深める契機にもなるでしょう。
保護者として、見極める目を持つ
保育園を選ぶとき、どうしても外見的な印象に引っ張られてしまうのは自然なことです。ですが、子どもの長い時間を預ける場所だからこそ、知っておいてほしいポイントがあります。
- 園のホームページや第三者評価報告書に、監査結果やその対応がきちんと掲載されているか
- 保育理念だけでなく、園運営の姿勢や財務状況の透明性についても情報公開しているか
- 保育士が長く働いているかどうか(職員の定着率は運営の健全さと直結します)
すべてを完璧に理解する必要はありません。ただ、子どもたちの育つ環境には、見えない部分にも丁寧に目を向けている人たちがいるということを、知っておいていただきたいのです。
保育士として、選ぶ力を持つ
これから保育士として働こうとしているあなたへ。
あるいは、今の職場を離れようとしているあなたへ。
保育士の仕事は、人と人との関係の上に成り立ちます。ですから、職場の人間関係や園の雰囲気はとても大事です。でもそれと同じくらい――いえ、もしかしたらそれ以上に大切なのは、「その園がどうやって成り立っているか」を知ることです。
お金の流れを正しく管理している園は、職員への給与支払いも安定しています。
書類をきちんと作成している園は、保育計画や記録も丁寧に作られています。
拠点間の運営が整っている法人は、他の園への異動や応援もフェアに行われています。
つまり、運営の“まじめさ”は、あなたの働きやすさにも、子どもたちの笑顔にも、すべてつながっているのです。
まとめ:「保育とは、“まじめさ”の連なり」
保育とは、毎日の小さな積み重ねの連続です。
おむつを替える。ごはんを食べさせる。お昼寝を見守る。絵本を読む。トイレに付き添う。泣いている子の背中をそっとなでる――。
そんな日々の中で、子どもたちは少しずつ、でも確実に育っていきます。
その日常を支えているのは、見えない場所にある“まじめな仕組み”です。
お金を正しく扱う。書類をきちんと残す。情報をオープンにする。そうした透明性が、保育の土台を支えているのです。
今回のGakkenほいくえん砧での指摘も、そうした“まじめさ”をもう一度整えましょう、というメッセージでした。
そしてそれは、これから保育園を選ぶ保護者にとっても、職場を探す保育士にとっても、確かな選択の指針となるはずです。
あなたの目が届かないところにも、まじめさがありますように。
そのまじめさが、子どもたちの未来をつくっていきますように。
<参考>世田谷区 指導検査について
https://www.city.setagaya.lg.jp/01044/1632.html#p4

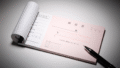

コメント